次回に続いて機械設計者にとって大変重要な材料知識について記事にします。今回は3回目です。材料の種類とその特徴などを纏めました。ぜひ最後まで目を通して頂き、ご自身の業務に役立てていただけたら幸いです。
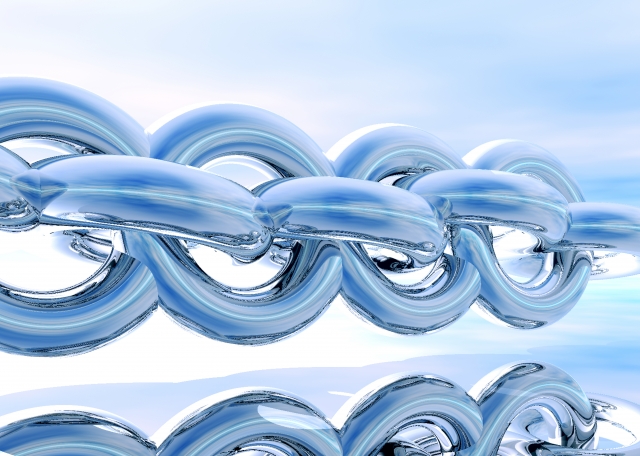
その①、②は以下のリンクより確認ください。
chuckmechanicalpe.com
材料の分類と特徴
金属材料
強度が大きいため、強度部材として使われることが多い。塑性加工や除去加工など加工性が良い。材料の中では重い分類になる。鉄鋼、非鉄金属などがある。
鉄鋼材料
純鉄、鋼、鋳鉄の3つに分類できる。それぞれ炭素量が異なる。
純鉄 C<0.02%
鋼 0.02%<C<2.1%
鋳鉄 2.1%<C<6.7%
純鉄とは数字からもわかるように鉄鋼材料の中でも最も炭素含有量が少なく、やわらかい材料。一般的な機械設計の範囲では使う機会はない。その柔らかさ故、加工が難しい材料としても知られている。
鋼は炭素量を調整することで様々な用途に使うことが出来る。純鉄よりも強靭で、加工性に優れている。
炭素鋼:低炭素鋼 C<0.25%
中炭素鋼 0.25%<C<0.5%
高炭素鋼 C>0.5%
合金鋼:低合金鋼 合金元素の総量が5%以下
中合金鋼 合金元素の総量が5~10%
高合金鋼 合金元素の総量が10%以上
炭素鋼
一般構造用圧延鋼材(SS材):炭素量0.3%以下の熱間圧延鋼材。SS###の#部分は引張強さの下限値が入る。熱処理を前提としていない。
機械構造用炭素鋼鋼材(SC材):炭素量0.08%~0.6%で、S##Cの#部分は炭素含有量(例えばS45Cなら0.45%)を表す。機械加工後、焼き入れ・焼き戻しなどの熱処理を想定している。硬さのある部品を作りたい場合に適している。S45Cは丸鋼、S50Cは角鋼が流通しており、形状に合わせて使い分けると良い。
炭素工具鋼鋼材(SK材):炭素量0.6%~1.5%で、SK##の#部分はSC材と同じで炭素含有量を表している。SK95が代表品種。名前の通り工具で使うことを想定して作られたため、耐摩耗性に優れている。0.6%以上になると硬さは向上しないが、耐摩耗性が向上する。工具以外にも広く利用されている。似た名前に高速度工具鋼(SKH材)があるが、これは合金鋼になるため詳細は割愛。SK材との使い分けは使用温度の違い。200度以下はSK材を用い、それより高い場合はSKH材を用いる。
合金鋼
合金鋼は炭素鋼の5大元素をベースに他の金属を加えたものです。合金元素にはCr、Ni、Mo、W、Coがあります。全体に共通して言えることですが、加える元素の種類が多いため、高価になる傾向があります。安価な産業ロボットやコンベア等には選択する機会が少ないかもしれません。
合金鋼は以下に分類できます。
ステンレス鋼
合金工具鋼鋼材
高速度工具鋼鋼材
機械構造用合金鋼鋼材
超硬合金
高張力鋼
ばね鋼
高炭素クロム軸受鋼
ステンレス鋼(SUS材):合金鋼の代表的存在。SUS###の#部は種類番号。引張強さや金属の含有比率を表しているわけではない。5大元素に加えてCr、Niを加えた合金。耐食性に優れている。酸素とクロムが結合することで酸化クロム膜(不動態皮膜)が生成され、酸素や水から金属を守っている。Crが13%以上ないと膜が生成されない。また、炭素含有量が多くなると、Crと結合し炭化物となるため、炭素鋼と比べて炭素の割合を減らしている。以下の3つに分類できる。
ーオーステナイト系:SUS304(18-8ステンレス)。括弧内の数字は18がCrの比率、8がNiの比率。他に比べてNiが入っている分高価だが、流通性が良いため、最もコストパフォーマンスが良いとされている。耐食性が他に比べ優れている。唯一磁性がない。しかし、塑性変形により組織が変わるため、磁性を帯びることに注意。引張強さは520MPa以上。
ーフェライト系:SUS430(18Crステンレス)。オーステナイト系に比べてNiが加えられていない。安価で強度、耐食性共に他品種と比べ中程度。引張強さは450Mpa以上。
ーマルテンサイト系:SUS410(13Crステンレス)。他と比べ安価で強度は高い。耐食性が他と比べて劣っているため、環境を選ぶ。炭素量が多いため、焼き入れにより高い硬度が得られる。SUS440Cは炭素量が1%でSUS材の中では最高硬度。引張強度は540Mpa。
合金工具鋼鋼材(SK#材):SK材から更に耐摩耗性、耐熱性、焼き入れ性に関して向上させた工具鋼。SKD材、SKS材、SKT材などがある。末尾の数字は種類番号を表す。
高速度工具鋼鋼材(SKH材):通称ハイス鋼。600度までは硬さが低下しないため、耐熱性に優れた工具鋼。
機械構造用合金鋼鋼材:焼き入れを行うことで、炭素鋼よりも機械的性質を向上させることを目的に作られた合金鋼。SCr材、SCM材、SNC材、SNCM材などがある。Sの後のアルファベットは含有元素を表します。SCM材はクロモリと呼ばれている。具体的な強化ポイントとしては、強度の向上、焼き入れ性向上(サイズが大きくても内部まで焼き入れ可能)。焼き入れを前提として用いる。剛性は鋼材と変わらない点に注意。
超硬合金:非常に硬い合金で、WCやTiCをCoで焼結した金属。高硬度、高強度、高耐熱性により、加工時間を短くすることが出来る。粘り強さが鋼材に比べて半分以下で、衝撃に弱い。
高張力鋼:ハイテン鋼ともいう。SS400と比べて2倍以上の引張強さを有している。炭素鋼にSi、Mn、Tiを含んでいる。柔らかさ、強さを兼ねそろえており、自動車のボディにも使用されている。
ばね鋼(SUP材):その名の通りばねに用いられる合金鋼。弾性範囲が広く降伏点(1080N/mm2以上)、疲労強度ともに高い。
高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ材):高炭素鋼にクロムを加えた合金鋼。その名の通り、軸受に使用される。よって耐摩耗性に優れている。
鋳鉄は炭素量が2%以上の鉄合金。一般的には炭素量が多いほど溶融温度が下がるため、鋳物に適している。鋼よりさらさらで、溶湯の流動性が良い、凝固収縮が少ない、型の転写性に優れているなどから鋳造性が良いとされている。全体的な弱点として溶接に弱い点が挙げられる。炭素量が多い材料は溶接性が悪い。
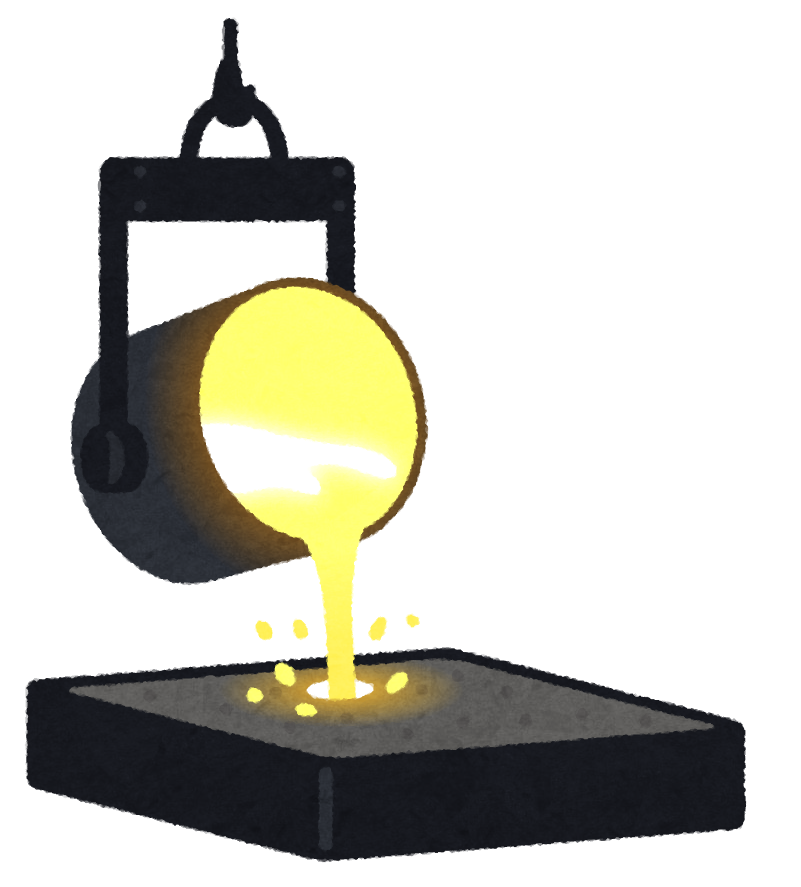
片状黒鉛鋳鉄(ねずみ鋳鉄)FC100、FC350など
球状黒鉛鋳鉄(ダクタイル鋳鉄)FCD350、FCD400など
白鋳鉄
鍛鋳鉄
片状黒鉛鋳鉄(FC材):FCはFeと鋳物を表すCastingを表す。後ろの数字3桁は引張強さを表す。組織を拡大してみると片状の黒鉛が分布していることからその名がついた。複雑形状で、強度を要しない構造体に使用される。切削性、振動吸収性、耐摩耗性に優れている。
球状黒鉛鋳鉄(FCD材):片状黒鉛鋳鉄にMgを加えることにより晶出する黒鉛が球状に見えることからその名がついた。片状黒鉛鋳鉄と比べ、切削性、鋳造性は悪いが、靭性に優れている。組織が球状のため、切削時は切り屑がきれない。高強度、高靭性を要する複雑形状体に使用される。SS400やS45Cなどと同等の強度を持つ。
非鉄金属材料
非鉄金属材料とは鉄以外の元素で構成された金属のこと。よく目にするものを中心に以下にまとめてみた。
アルミニウム合金
マグネシウム合金
銅合金
チタン合金
アルミニウム合金:非鉄金属の中で最も有名な材料。1円玉にも使われている。機械加工用(A####)と鋳造用(AC##)で記号の付け方が異なる。アルミニウム合金はその成分によって様々な用途に使い分けられる。一般的に用いられるA5052はSS400と比べ密度が1/3とその軽さが特徴的。その分引張強さは劣るが、合金の種類によってはSS400よりも強い材料(A7075:超々ジュラルミン)も存在する。ただし、剛性はどの合金を見てもさほど変わらないため、堅牢な構造体には不向き。その他機械的性質において、鉄鋼材料とは異なる性質が多くあり、別物として知識をインプットする必要がある。材料の後に調質記号がつくのも特徴である。アルミニウム合金は汎用的なA5052を見ても鉄鋼材料と比べて高価なため、その特性を生かせる場面で利用したい。
1000系 純Al カバーなど
2000系 Al-Cu-Mg系合金 ジュラルミンケースなど
3000系 Al-Mn系合金 化学容器など
4000系 Al-Si系合金 ピストン、ろう材など
5000系 Al-Mg系合金 機械の構造用部品など
6000系 Al-Mg-Si系合金 押し出し材など
7000系 Al-Zn-Mg系合金 航空機気体など
8000系 その他合金
マグネシウム合金:金属の中で最も密度が小さく軽い材料。鉄の1/4でノートパソコンなどの筐体に使われている。加工性が悪いため、ダイカストが適している。また振動を吸収する特徴をもつ。マグネシウム単体では、アルミニウム合金に含まれるなど活用の場が多々ある。弱点としては弾性率が低い、疲労強度が低い、摩耗に弱い、酸化・発火しやすいなどが挙げられる。
展伸用マグネシウム合金 ━Mg-Al系 Al3~7%、Zn1% AZ31,AZ61など
┗引張強さは最大250Mpa。航空機、自動車などで利用。
━Mg-Zn-Zr系 Zn1~3% Zr0.5% ZK60A
┗引張強さは最大250Mpa。熱処理により耐力が向上。
┗比強度が強い。
鋳造用マグネシウム合金 ━Mg-Al系 Al6~9% Zn1~3% わずかにMn AZ63,AZ91など
┗T6処理で280Mpaの引張強さが得られる。
┗エンジン部品などに使用。
━Mg-Zn系 Zn3~6% Zr0.5~1% ZK61,ZE41Aなど
┗ZK61はT6処理で引張強さ315Mpa。
┗自動車のエンジン部品などに使用。
高分子材料
きわめて分子量の多い分子を高分子と呼び、高分子材料としてはゴムやプラスチックなどがある。ここでは主にプラスチックについて説明する。金属材料と比べ強度は低いが、加工しやすい、軽いなどの特徴がある。アウトガスや環境汚染などの問題と向き合いながら使用しなければならない。プラスチックは種類が多いため大分類のみ触れて詳細は別途解説記事を掲載予定。
まずは加熱した際の特性を見てみる。以下の2つに分類できる。
熱可塑性プラスチック 加熱によって軟化する。
再利用が可能で、環境にやさしい。
プラスチックの9割を占める。
熱硬化性プラスチック 加熱によって硬化する。
再利用できないため、廃棄が難しく環境に負荷を与える。
次に、プラスチックの中でも機械的性質を見てみる。以下の2つに分類できる。
汎用プラスチック:引張強さ49N/mm2未満もしくは耐熱温度100℃未満
┗ポリエチレン(PE)
┗ポリプロピレン(PP)
┗ポリ塩化ビニル(PVC)
┗ポリエチレンテレフタレート(PET)
┗フェノール樹脂(PF)
┗ポリスチレン(PS)
エンジニアリングプラスチック:引張強さ49N/mm2以上かつ耐熱温度100℃以上
┗ポリイミド(PI)
┗ポリカーボネート(PC)
┗ポリアミド(PA) ※ナイロンともいう
┗ポリアセタール(POM) ※ジュラコンともいう
スーパーエンジニアリングプラスチック:エンプラよりも耐熱温度を向上(150℃)
┗ポリエーテルイミド(PEI)
┗ポリアミドイミド(PAI)
┗ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
先にも述べた通り、機械的性質において金属材料よりは劣るが、その種類の多さだけ様々な特性を有した材料があり、選択の幅が広いという利点がある。別記事にて、各プラスチック材料に関する特徴をまとめる予定。
無機材料
無機材料とは無機物質で構成される材料。ここではセラミックスについて説明する。
セラミックスは簡単に言うと陶器のような焼き物です。材料を見てみると土や粘土といった材料がある。いくつか代表的な材料を挙げてみる。
アルミナ(Al2O3):酸化アルミニウム。代表的なセラミックス材料。
窒化アルミ(AlN):窒化アルミニウム。熱伝導率が高い。
炭化ケイ素(SiC):耐食性が高い。耐熱性が他と比べて高い。
炭化タングステン(WC):非常に硬く、研磨剤や切削工具に用いる。
セラミックスの特徴として硬く、耐熱性があり、耐食性がある点が挙げられる。特に硬さに関してはものによってはダイアモンドに次ぐ硬さとされているため、これが加工が難しいというデメリットにもなる。最近はアディティブマニュファクチャリングによる部品製造も可能になってきており、用途が拡大している。
複合材料
複合材料とは、マトリックス材に教科繊維などの材料を組み合わせることで、母材本来では達成できない機械的特性の改善することを目的として生み出された材料。一般的に複合材料というと組み合わせ次第で多岐にわたるため、今回は繊維強化プラスチック(FRP)について説明する。
ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)━強化繊維にガラス繊維を用いている。
┗電波透過性がよい。難燃性が向上
カーボン繊維強化プラスチック(CFRP)━強化繊維に炭素繊維を用いている。
┗GFRPと比べて強度が高い。
FRPは製造方法が他の材料とは異なるため、コスト感覚などは新たに身につけるつもりで 学習したい。例えば、マトリックス樹脂と強化繊維は一層ずつ重ね合わせる必要があるため、厚みが増えれば成形時間も増え、コストがその分増加する。さらに、異方性を理解することで、必要最低限の強度を持たせた部材の選定が可能になりコストダウンが図れる。FRPは鉄鋼材料よりも強く軽く剛性が高いという夢のような素材だが、安易に使用することは決して許されない材料である。
最後に
ちょっと長くなりましたが、無理に覚える必要はありません。まずは知ることを優先して、ゆっくり何度も読んでいただけたらと思います。選定の際、この特徴に該当する材料は確か・・・といった具合で、都度調べればいいのです。重要なことはインデックスを作る。必要な時にさっと取り出せるようにインプットしておけば、設計時間の短縮や周りが思いつかないような設計案の提案が出来るかもしれません。
次回は材料の加工について記事にします。